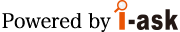よくあるご質問
他の電子債権記録機関で発生させた電子記録債権を、でんさいネットで利用することはできますか。
「特定記録機関変更記録」をすることにより、でんさいネットと提携した他の電子債権記録機関(提携記録機関)で発生させた電子記録債権をでんさいネットに移動し、「でんさい」として取り扱うことができます。
特定記録機関変更記録によりでんさいネットに移動した「でんさい」については、お客さま(でんさいの債権者)のご利用の参加金融機関に割引(注)に出すこと等が可能となります。
(注)でんさい割引の取扱可否は、参加金融機関で異なります。
なお、でんさいネットの「でんさい」は、他の電子債権記録機関に移動することはできません。
【詳細説明】
でんさいネットと提携した他の電子債権記録機関(提携記録機関)で発生させた電子記録債権をでんさいネットに移動し、「でんさい」として取り扱いたい場合、当該電子記録債権の債権者は、債務者の承諾を得て、提携記録機関に特定記録機関変更記録の請求を行います。
請求を受けた提携記録機関は、でんさいネットに当該電子記録債権の内容等を通知しますので、でんさいネットでは、特定記録機関変更記録として当該電子記録債権の内容等を記録します。
上記の特定記録機関変更記録後、当該電子記録債権は「でんさい」として利用可能となり、債権者は、でんさいネットの参加金融機関へ当該でんさいを譲渡することにより資金化(割引等)すること等が可能となります。
なお、特定記録機関変更記録を請求するためには、債権者および債務者が、提携記録機関およびでんさいネットの双方と、特定記録機関変更記録が利用可能な契約を締結しておく必要があります。
また、債権金額が1万円未満または移動する電子記録債権がでんさいネットで取扱いできない内容である場合(債権金額が100億円以上である場合、支払方法が分割払いである場合等)のほか、次の事由に該当する場合は、特定記録機関変更記録を請求することができません。
〇 債権者および債務者の決済口座(利用契約)のいずれかが、債権者請求方式による発生記録が請求できない場合
〇 記録機関変更記録をすることができない場合(提携記録機関で発生させた電子記録債権に、記録機関変更記録を制限する旨の記録がされている場合)
〇 発生記録に記録されている債権者以外の者が債権者である場合
〇 発生記録に記録されている債務者以外の者が債務者(電子記録保証人を含む)である場合
〇 銀行営業日以外の日が支払期日である場合
〇 支払等記録、質権設定記録、分割記録、記録機関変更記録、信託の電子記録、強制執行等の電子記録がされている場合
〇 債務者が指定許可機能を利用している場合で、債権者を発生記録(債権者請求方式)の指定許可先として登録していない場合
〇 債権者および債務者のいずれかが、発生記録の請求を制限されている場合
〇 提携記録機関が定める場合
・業務規程第37条の2
・業務規程細則第32条の2
・業務規程細則第32条の3
・業務規程細則第32条の4