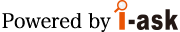よくあるご質問
中小受託取引適正化法(通称 取適法(2026年1月1日施行))において、でんさいを支払手段として利用するに当たって、特に留意すべき事項はありますか。
取適法の適用対象となる取引においても中小受託事業者への製造委託等代金の支払手段としてでんさいを利用可能ですが、この場合には、でんさいの満期日(電子記録債権法第16条第1項2号に規定する期日をいいます。)や各種手数料の負担について留意が必要です。具体的な留意事項については以下のとおりです。
※取適法では適用基準に「従業員数」、対象取引に「特定運送委託」が追加されています。取適法の適用対象となる取引・基準や同法の詳細な内容等は公正取引委員会のウェブサイトをご参照ください。
※でんさいの利用に係る主な留意事項をまとめた資料および取引先への案内状サンプルは当会社のニュースリリースをご参照ください。
(取適法の適用対象ではない取引は、以下の留意事項の対象とはなりません。)
【満期日の制限】
取適法では、中小受託事業者が、取適法の支払 期日(製品や役務の受領日(納品日)から起算して60日以内)までに、製造委託等代金を金銭で満額受領できるようにする必要があります。でんさいの満期日(中小受託事業者側への入金日)も、原則として、この支払 期日内で設定してください※。
※ 満期日が取適法の支払 期日より後に設定されたでんさいについては、支払側が割引料等を負担する場合であっても、受取側が自ら割引を受ける等の行為が必要になる場合には、使用が認められません。
なお、でんさいの満期日が金融機関の休業日と重なる場合、事前に中小受託事業者との書面合意があれば、2日間までは順延が認められます。
【入金手数料を委託事業者が負担】
金融機関によっては、でんさいの口座間送金決済による入金にかかる手数料(金融機関によって「受取手数料」または「決済手数料」などの名称でも設定されています。以下「入金手数料」といいます。)が発生する場合※があります。
※ 入金手数料の設定有無、設定されている場合の手数料額等は、中小受託事業者又は中小受諾事業者の取引金融機関へご確認ください。
この入金手数料を中小受託事業者が負担する場合には、中小受託事業者が製造委託等代金を満額受領することにはなりません。したがって、委託事業者が製造委託等代金に入金手数料を加えた金額を(または入金手数料相当額を別途)支払い、中小受託事業者が製造委託等代金を取適法の支払 期日までに満額受領できるようにする必要があります。
【発生記録手数料を委託事業者が負担】
(債務者請求方式の場合)
債務者請求方式によるでんさいの発生記録手数料は委託事業者が負担する必要があり、同手数料を製造委託等代金から差し引いて支払うことは認められません。
(債権者請求方式の場合)
債権者請求方式では、通常、債権者がでんさいの発生記録手数料を金融機関に支払うこととなります。
中小受託事業者が債権者として発生記録を請求した場合の同手数料を当該中小受託事業者が負担する場合には、中小受託事業者が製造委託等代金を満額受領することにはなりません。したがって、委託事業者が製造委託等代金に当該発生記録手数料を加えた金額を(または受取手数料相当額を別途)支払い、中小受託事業者が製造委託等代金を取適法の支払 期日までに満額受領できるようにする必要があります。
【支払 期日より前に行う割引等の取扱い】
委託事業者が取適法の支払 期日以前にでんさいの満期日を設定し、支払 期日までには製造委託等代金の満額の金銭が、自動的に中小受託事業者の口座に振り込まれる状態となっていれば、中小受託事業者が満期日より前に行う割引等に関する制約はありません。この場合、同満期日より前に割引または譲渡を行う場合の割引手数料または譲渡手数料は、これまでどおり債権者(中小受託事業者)が負担することとなります。
なお、でんさいのシステム上、当社や金融機関は、利用者間のでんさいによる取引が取適法に該当する取引か否かを判別することはできません。